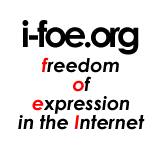準備書面(3)(2006/04/14)
原告側準備書面(3)
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
html化に際し、○に数字は1)、2)などに置き換え、○にカタカナは(ア)、(イ)などに置き換えた。これらは、機種依存文字で、そのままにすると表示環境によって文字化けするからである。
平成17年(ワ)第914号・平成17年(ワ)第3375号反訴
原告(反訴被告〉 松 井 三 郎
被告(反訴原告) 中 西 準 子
準備書面(3)
2006年4月14日
横浜地方裁判所 第9民事部合議係 御中
原告(反訴被告)訴訟代理人弁護士 中下裕子
同 弁護士 神山美智子
同 弁護士 長沢美智子
同 弁護士 中村晶子
記
被告の2006(平成18)年1月25日付「準備書面2」に対する反論は 以下のとおりである。
1 本件記事の摘示事実に関する被告の主張(準備書面2の3項、4項)に対する反論
(1)本件が事実を摘示しての名誉毀損であることは、原告準備書面(2)に述べ たとおりである。
本件記事のうち原告が問題にしている「最初の情報発信に気をつけよう」の記載部分は、大きく分けて、
1) 原告が「次はナノです」という発言をした、被告がそれを聞いて驚いた、 その発言は要するに「環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」という意味であるとして、原告の発言の意味を問題とする部分(訴状 第2請求の原因2(1)1)の記載)
2) 原告が新聞記事のスライドを用いて行ったプレゼンテーションの仕方を問題とする部分(訴状 第2請求の原因2(1)2)の記載)の2つが柱となっていることは明らかである。
(2)被告は、本件記事の主要な部分はナノ粒子の有害性についての問題提起の仕方に関する批判であり、上記1)の部分について、内容のほとんどがナノ粒子についての記事であり環境ホルモンについては「環境ホルモンは終わったという意味である」の11文字(ママ)しかないからという理由で名誉毀損にあたる事実摘示ではない旨の主張をしている。
しかし、記事の主要部分であるかどうかや名誉毀損の摘示事実に該当するかどうかは、単に文字数だけで決まるものではないことは言うまでもないことである。例えば、「犯罪者」や「スパイ」などの記述は、文字数は少なくても名誉毀損の摘示事実に該当するのは当然である。
(3)原告が「環境ホルモンは終わった」という意味で発言したかどうかは、以下のようなこの問題をめぐる意見の対立状況を勘案すると、極めて重要な問題であり、その意味で、まさに主要部分に他ならない。
すなわち、いわゆる環境ホルモン問題は、人工の化学物質が人間や野生生物のホルモンの働きをかく乱し、さまざまな悪影響を及ぼしているのではないかということが懸念されている問題である。従来の作用量よりもずっと微量でも影響を及ぼす可能性があること、複合的影響も懸念されること、胎児期など特に化学物質に対する感受性が高くなる時期があり、その時期を過ぎると同じ量の化学物質を浴びても悪影響が現れないことを指摘する研究報告もあること、化学物質を浴びた時期(例えば胎児期)と悪影響が発現する時期(例えば思春期との間に相当の時間差があることが指摘されていることなど、従来の発ガン性などの毒性概念にはない、新たな特徴をもった課題であるとされている。
このような環境ホルモン作用が発見されたのは比較的最近で、日本では、コルボーンら著『奪われし未来』(翔泳社)が1997年9月に刊行されて以来、一挙に社会的関心が高まり、科学的研究も始められるようになった。しかし、未だその研究は緒に就いたばかりであるうえ、前述のような環境ホルモンの作用の特徴からも、そもそも短期間のうちに全容が解明されるという性質の課題ではないこともあり、まだまだ未解明な点が数多く残されているという状況である。原告は、国際シンポジウムでのプレゼンテーションの冒頭に、「わからないことがいかに沢山あるかがわかった」という環境省の上家課長の発言を引用し、環境ホルモン研究の現状を一言で説明しているが、まさにそのような状況にあったのである。
こうした状況下にあって、「環境ホルモン問題は大した問題ではない」という意見から、「未解明なことは数多くあるが、人間や野生生物にとって看過できない重大な課題である」という意見まで、専門家の間でも大きく意見が対立している。前者の意見は、産業界の研究者や、被告のような環境ホルモン研究の専門家ではない学者・ジャーナリストが主張していることが多く、原告をはじめ環境ホルモン研究者の多くは、むしろ後者の立場に立っている。
被告は、1998年12月号の『新潮45』という雑誌に、「環境ホルモン空騒ぎ」と題する文章を執筆して以来、その後も折に触れて、上記前者のような意見を繰り返し主張してきていたものであり、一方原告は、既述のとおり、文科省の3カ年にわたる特定領域研究「内分泌撹乱物質の環境リスク」の代表を務め、100名近い博士号取得者を輩出するとともに、国際的にも著名な環境ホルモン研究の第一人者であり、後者の意見を代表する研究者の1人であった。そして、本件シンポジウムの第6セッションにおいては、パネリストの中に環境ホルモン研究の専門家は原告1人という状況であったことは既述のとおりである。
このように、環境ホルモンのリスク認識をめぐっては、大きく2つの異なる意見の対立があり、本件シンポジウムにおいて、被告は、前者、すなわち「環境ホルモンは終わった、大した問題ではなかった」の認識に立って、環境ホルモン問題の功罪」や「リスクコミュニケーションの失敗」を統括しようとしていたが、原告は、これとは異なる認識に立って、自らの環境ホルモン研究の 最新成果(ダイオキシンの毒性メカニズムに関する仮説)を紹介し、未解明なことは多いが、懸念を持ち続けて研究を続けるべき重要な課題であることを主張したものである。
本件記事においては、その国際シンポジウムにおける原告のプレゼンテーションについて、こともあろうに原告が、「環境ホルモンは終わった。次はナノだ」と発言したなどと事実に反する記載をされたのである。対立する意見の一方の雄と目され、その輩下に数多くの研究者を抱え、「環境ホルモン学会」の副会長という重責を担う原告にとっては、このような事実記載が極めて重要な意味を持つことは当然であろう。そして、このように日頃からの原告の発言や信条と全く相反する発言を行ったかのように記載されることは、研究者としての信用や社会的評価を著しく低下させるものであることは明らかである。
(4)さらに、環境ホルモンは終わった」という記載が決して取るに足らない記述などではないことは、被告自身の主張からも明らかである。
すなわち、被告は、1)について、「原告の発言の趣旨を『社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』というものと受け止めたということである。」と自ら認めたうえで、さらに、「『(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』かどうかは、研究者に共通する重要なことであり、被告としても見逃せない発言である。」から、「そのような重大な問題提起」をしたと主張しているのである(被告準備書面2、p4最終行〜、同p5、10行目〜)。
つまり、被告は、原告のプレゼンテーションの仕方だけでなく、発言の趣旨すなわち意味内容を問題とし、「研究者に共通する重要なこと」「被告としても見逃せない発言である」として、原告の「つぎはナノです」という発言とその意味に重大な関心を寄せ、見逃せないと考えたからこそ、「要するに、環境ホルモンは終わった…という意味である」とわざわざ強調しているのである。
被告自身がそのような認識で本件記事を執筆しているのであるから、本件ホームページの読者は、「要するに、環境ホルモンは終わった…という意味である」との被告の強調の意図を酌んで、この部分が被告の強調したい重要な部分であると受け止めるのは当然であろう。
したがって、この部分の記載は、文字数としては11文字(ママ)にすぎないとしても、被告自身も主張するように、決して「見逃せない」「重大な問題提起」に他ならず、まさに主要部分のひとつであることは明らかである。
(5)2)については、被告自身が、本件記事において原告の新聞記事のスライドを用いてのプレゼンテーションの仕方について問題にする趣旨であったことを認めているところである。被告が誤った事実を摘示したこの記載によって読者に伝えようとした趣旨は、自身が準備書面中に何度も繰り返しているように、「このナノ粒子の発表の仕方が、『唐突でお粗末であった』」(被告準備書面2、p4、13行目)、「『お粗末な形で行われた』(同p5、13行目圧「原告のナノ粒子についての問題提起の仕方があまりにお粗末」(同p6、p11)というものである。
被告自身が認めているように、本件記事の2)の部分は、原告のプレゼンテーションの仕方に対して批判するものである。そして、その批判記事によって、「原告のナノ粒子についての問題提起の仕方があまりにお粗末」(下線部原告代理人)であることを読者に伝えようとしたことは前述のとおりである。つまり、このような批判をすることによって、原告が、専門家としての基本的資質さえ疑われかねない、極めて不名誉な評価を受けるであろうことは、被告には容易に理解できていたはずであるし、むしろ、被告は、そのような不名誉な評価を読者に伝えようとして、本件記事を記載したのである。
言うまでもなく、他者に対する名指しの批判というものは、常に名宛人とされた者に対して、一定程度の社会的評価を低下させるものである。もちろん、そうであっても、正しい事実に基づく建設的批判であれば、学問や民主主義の進展という観点から大いに推奨さるべきは当然である。しかし、逆に、もし事実に反する批判がホームページなどで一方的に行われるならば、いとも簡単に個人の名誉が侵害されることになりかねないのである。つまり、「学問的批判」の名の下に、他者の人格を攻撃し、その社会的評価を貶めることも、極めて容易なことなのである。
こうした「批判」のもつ内在的危険性を考えると、批判の自由を行使しようという者は、常に事実に基づく正しい批判であるかということについて、厳しく自らを戒める必要があることは当然であろう。特に、被告のような、高名で社会的地位の高い研究者が批判する場合には、読者に与える影響は甚大なものであるから、よほど細心の注意をもって事実を正しく把握し、伝えるようにしなければならないのは当然である。さらに、自らが過ちを犯す可能性もあることを自覚して、名指しで批判を行う場合には、できるだけ、一方的な方法ではなく、必ず相手からの反論の機会を保障する必要がある。このようなことは、学者同士の批判の場面においては、基本的な原則であるが、本件記事における被告の批判の方法は、明らかにこれに反している。
しかるに、被告には、このような批判に対する謙抑的な姿勢もなければ、基本原則違反によって他者の名誉を傷つけたことに対する反省も全くないのである。そのことは被告の摘示事実についての主張態度にもよく現れている。本件批判の対象たる前提事実についての被告の主張は極めて曖昧であると言わざるを得ない。すなわち、被告の主張によれば、原告が1)新聞記事のスライドを見せて、2)「次はナノです」という趣旨のことを言ったことが前提事実であると主張し、さらに言えば、3)新聞記事以外に原論文の指摘及びその問題点の指摘が欠落していたこと、4)新聞にこう書いてあるが自分はこう思うといった発言も欠落していたことも前提事実とする余地があるかもしれないなどと主張する(同準備事面1の3項)。しかし、これだけを前提事実にして、前述のような「あまりにお粗末」などというような手酷い批判をしてもよいと、被告は本気で考えているのだろうか。
原告は、準備書面(1)においても、同(2)においても、被告の前提事実に関する主張は誤りであると指摘してきた。しかし、被告は、今回の準備書面2においても、前提事実についての原告の主張にはまともに反論せず、今度は、「主要部分ではない」という新たな主張を突然持ち出してきたのである。しかも、一方では「主要部分ではない」と主張しながら、他方で「『(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』かどうかは、研究者に共通する重要なことであり、被告としても見逃せない発言である」などと相矛盾する主張を平気で行っているのである。このような訴訟態度に、学者として、また人間としての被告の不誠実な態度がよく現れているといえよう。被告におかれては、今一度、本件記事の記載によって他者の名誉を侵害したという事実を重く受け止め、自らの過ちを真摯に反省されることを強く求めたい。
原告は、念の為、本件批判記事で摘示された明示・黙示の事実について、以下のとおり詳述する。
2 本件記事の摘示事実について
(1)被告ホームページ上の本件記事は、環境省主催『第7回 内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム』を終わって−(環境ホルモンの)リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任−」という意味の表題のもとに、5つの小見出しを付した本文において、表題のテーマに沿って環境ホルモン問題に関するリスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任をめぐって展開されている文章であり、原告が問題にしている部分は、このような内容と流れで記載された一連の文章の最後の部分である。
被告はここで環境ホルモン研究の専門家であり環境ホルモン研究を推進してきた研究者である原告を名指しして次のような記載をしているのである。
記載1)「パネリストの一人として参加していた、京都大学工学系研究科教授の松井三郎さんが、新聞記事のスライドを見せて、『つぎはナノです』と言ったのには驚いた。要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」
記載2)「スライドに出た記事が、何新聞の記事かは分からなかったし、見出しも、よく分からなかった(私の後ろにスクリーンがあり)ナノ粒子の有害性のような記事だったが、詳しくは分からなかった(読みとれなかった)。・・・
その論文だと思ったのだが、帰宅して新聞記事検索をかけると、New York Times等などには出てくるが、日本の一般紙には出ていない。したがって、別の論文の紹介のようである。その内容がどういうものかは分からないのだが、いずれにしろ、こういう研究結果を伝える時に、この原論文の問題点に触れてほしい。
学者が、他の人に伝える時、新聞の記事そのままではおかしい。新聞にこう書いてあるが、自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべきではないか。情報の第一報は大きな影響を与える、専門家や学者は、その際、新聞やTVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。でなければ、専門家でない。」
(2)記載1)の摘示事実
ア.被告は、記載1)で、直接的には次の事実を摘示している。
A 原告が、新聞記事のスライドを見せて、『つぎはナノです』と言った。
B 被告は、この発言を聞いて驚いた。
なぜなら、この発言が、「要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」という意味だったからである。
イ.被告ホームページの読者の普通の注意と読み方とを基準として、表現方法等も検討した上、前後の文脈等の事情を総合的に考慮し、間接的ないし婉曲的、黙示的に主張していると見られる事実を補うと、1)の摘示事案は次の通りとなる。
A’ 原告が、環境省主催「第7回 内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」(04.12.15〜17 於:名古屋)の第6セッション「リスクコミュニケーション」において、パネリストとしての発言にあたり、新聞記事のスライドを見せて、『つぎはナノです』と言った。
B’ 被告は、この発言を聞いて驚いた。
なぜなら、この発言は、要するに「環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」という意味であったからである。
原告は、これまで環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張してきた研究者であり、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗に責任のある学者の一人である。(リスクコミュニケーションが失敗だったか、仮にそうだとしてその責任は学者にあるのかについては異論のあるところであるが、ここでは被告の見解を前提に記述する。)
にもかかわらず、研究者に共通の重要な問題について、簡単に宗旨替えをし、また環境ホルモン騒動の責任をとることもなく、「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」という意味の発言をして、新たな危険情報の発信をしたからである。
ウ.A’B’のような事実摘示は、本件記事の読者に対して、「原告は、環境ホルモン学会副会長・文部科学省特定領域研究班『内分泌攪乱化学物質の環境リスク』の代表を務めるなど、これまで環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張し、環境ホルモン問題があたかも大変な問題であるかのような情報発信をし、また増幅してきた研究者の一人であって、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗に責任のある学者であるにもかかわらず、手のひらを返したように宗旨替えをし、『(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』という趣旨の発言をして、環境ホルモン騒動の責任をとらないままに、新たな危険情報の発信をしている」
「原告が、環境省主催の国際シンポジウムという公の場において、研究者に共通する重要なことがらについて、高名な学者である被告も見逃せないような節操の無い発言をした」という、研究者としてきわめてマイナスの誤った印象を与えるものである。
(3)記載2)の摘示事実
ア.被告は、記載2)で、次の事案を摘示している。
C 原告は、前記シンポジウムのセッションにおいて、パネリストとして発言するにあたり、新聞記事のスライドを見せて、ナノ粒子の有害性に関する論文の紹介、これについての研究結果を伝えるプレゼンテーションを行って、ナノ粒子の有害性の問題提起をした。
D その問題提起の仕方は、何新聞の記事か分からず見出しもよく分からない記事を示して、原論文の問題点に触れずに新聞記事そのままを紹介するだけのものであった。
研究者は、研究結果を伝えるとき、新聞にこう書いてあるが自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべきであるのに、それをしなかった原告のプレゼンテーションの仕方は、唐突でお粗末であり、専門家のそれではなかった。
イ.このような事実が摘示されていることは、本件記事(甲1)の文面上明らかであるとともに、被告自身が被告準備書面(2)おいて、「本件記事におけるナノ粒子についての事実摘示が、1)原告が新聞記事のスライドを見せて『次はナノです』として、ナノ粒子の有害性を問題提起しながら、2)新聞記事の紹介以上に自分の考えや原論文を読んでの意見などを付加したものではなかったということに尽きる」(同準備書面p3(5))、「ナノ粒子についての発表の仕方が唐突でお粗末であった」(同書面p4(7)6行目)と主張していることからも明らかである。
すなわち、被告は、このような事実摘示を行う意図で2)部分を書いたものであり、本件記事の読者はまさに意図どおりの意味を読み取るのである。
ウ.このような事実摘示は、本件記事の読者に対して、「原告は、環境省主催の国際シンポジウムという公の場において、論文を紹介してナノ粒子の有害性について問題提起を行ったが、その際何新聞の記事なのか、また見出しもよく分からないような新聞記事を、原論文の問題点に何ら触れることなくそのまま使って、専門家としてするべき情報発信をすることなく、唐突でお粗末なプレゼンテーションを行った。
原告は、研究者のイロハであるプレゼンテーションの仕方も知らない学者であり、専門家の名に値しない。」との誤った印象を与えるものである。
(4)被告による以上のような事実摘示により、本件記事の読者に、原告があたかも、「研究者に共通する重要な問題について研究者としての基本的スタンスを節操なく変える学者である」、「研究者のイロハであるプレゼンテーションの仕方も知らず、唐突でお粗末な発表しかできない、専門家の名に値しない学者である」かのような誤った印象を持たれることにより、研究者としての社会的評価を著しく低下させられ、名誉を侵害されたものである。
3 前提事実は真実でないこと
上記のような前提事実が到底真実ではないことは、以下のとおりである。
(1)第6セッションは、専門家向けのもので座長2名(被告、京都大学内山巌雄教授)、パネリスト5名で構成されていた(乙4、p9、11〜12)。このうち、木下冨雄氏は社会科学者、吉川肇子氏は心理学者、山形浩生氏は評論家・翻訳家、日垣隆氏はジャーナリスト・作家である。山形氏は「環境危機をあおってはいけない」(文藝春秋社)の訳者であり(乙4、p21)自らセッションでも述べておられるようにおそらくその立場からの発言を期待されての登壇であると思われる(乙5〜2、p8最終行〜)。そのことは予め配布された山形氏のアブストラクト(乙4、p50)からも予想できた。また、日垣氏は、「日本のマスメディアで初めてダイオキシン騒動の行き過ぎを指摘」(乙4、p21)したジャーナリストの立場での登壇であると考えられる。
原告は、セッションが被告、山形氏、日垣氏の論調に終始してしまうことを懸念し(甲4ー2)、パネリスト中唯一の環境ホルモン物質研究の専門家として、環境ホルモン物質の研究の成果と、今後環境ホルモン物質研究をどのように進めていくのかについても述べなければならないと考えた。
(2)原告のアブストラクト(乙4、p52)は、このような考えに基づき、この5年間で内分泌攪乱化学物質研究が新しい知見を生み出したこと、DNAマイクロアレイ技術が可能にしたことと研究成果の例、内分泌攪乱化学物質問題は環境汚染研究と同時に生命化学のDNAレベルにおける基本的疑問を解明することを必要としていること、化学産業によって製造される有害化学物質、内分泌攪乱化学物質のリスクコミュニケーションをどのように進めるか、リスクコミュニケーションを必要とする新規化学物質の一例としてナノ粒子を挙げている(アブストラクトでは「ナノテクノロジー材料として注目されているフラーレンやナノチューブ」と記載している)。
(3)そして原告は、本セッションで、このアブストラクトに基づいて、要旨、次のような発言をした。これまでの内分泌攪乱化学物質研究で分からないことがいかに多いかということがわかったこと、マイクロアレイという新しく最重要な情報獲得手段ができたこと(以上乙5ー2、p12)、これによって化学物質の働きは多面性を持っておりあるひとつのエンドポイントだけではある物質の作用は評価できないことがわかったこと、そこから原因があってあるひとつの結果があるというような簡単な話ではないことが分かり思考方法を見直さなければならなくなったこと(以上同p13)、原告の具体的な研究成果(尿中にダイオキシンは出ず、インディルビン・インディゴが出てきたが、これがダイオキシンの排出機構との関係で非常に興味深いこと)、環境ホルモンの研究によっていままでわかっていなかった生命の秘密が同時に理解されてきているがまだまだわからないことが多いこと(以上同p14〜15)、これまでリスクコミュニケーションが下手であったが実はそれは生命の本質そのものがわからず難しい問題に直面していたことによること、最後にこれまでの環境ホルモン研究の成果を今後予防的に応用できる一事例としてナノ粒子に触れ、制限時間が来たので終了した(以上同p15)。
これらはすべて、これまでの内分泌攪乱化学物質研究で分かったことと分からないこと、研究成果の一端を紹介し、環境ホルモンの研究によって今までわかっていなかった生命の秘密が同時に理解されてきているがまだまだわからないことが多いのでさらに解明していきたいという方向性を打ち出した発言である。
そのうえで、最後に「我々は予防的にどうやって次の問題に繋げるのか。今回学んだ環境ホルモンの研究はどうやって生かせるのか。私は次のチャレンジはナノだと思っています。」との発言をした(乙5ー2、p15の反訳は「比べるのか」になっているが「繋げるのか」の誤記である。)。これは、環境ホルモン物質の一つであるダイオキシンの毒性機構と細胞外への排泄についての原告の研究室が解明した知見が、ナノ粒子の問題の解明に生かされると考えられることの付言であり、環境ホルモンは終わった、次はナノ粒子だ」などという趣旨の発言では全くない。
(4)このように、原告が、本セッションで「環境ホルモンは終わった」などという発言は一切していないことは、原告の発言を聞いていれば難なく分かることである(乙5ー2)。そもそも、被告は座長として、各パネリストのアブストラクトを事前に見て、意見まで述べているのであるから(甲4)、原告の発表の趣旨は予め了解していたはずであり、またそうでなければならなかった。座長の場にあるものとして原告のアブストラクトを精読したうえでセッションに臨み、かつ原告の発言を注意深く聞いていれば、原告が環境ホルモンは終わった」などという発言をするはずはないことも、実際そのような発言をしていないことも、容易に分かったはずなのである。
原告の発言の意図を理解することが困難なことではなかったことは、専門家向けの本セッションの聴衆であった環境ホルモン問題の専門家たちも、原告の意図を正しく理解し、なんの違和感もなく原告の発言を聞いたとみられることからも明らかである。本セッションでの会場からの質問・意見は日垣氏、山形氏、木下氏の発言と被告の取り纏めにだけ向けられ(乙5ー2、p29〜37)、原告の発言を聞きとがめての質問・発言は一切無かった。また、最初の質問者である国立環境研究所の堀口氏(同p29)、化学品安全管理研究所の大島氏(同p31)は原告の発言に賛同しこれを引用しながら他のパネリストへの質問ないし意見を述べているのである。
(5)また、前記2(3)記載の通り、被告は、原告が、新聞記事のスライドを見せて、ナノ粒子の有害性に関する「論文の紹介」、これについての研究成果を伝えるプレゼンテーションを行って、「ナノ粒子の有害性の問題提起を行った」旨の事実を摘示している。しかし、上記3(3)に述べたように、原告は、原告の研究室が解明した知見が最近話題となっているナノ粒子の問題の解明に生かされると考えられると付言したのみであって、ナノ粒子の有害性の問題提起をしたり、それについての論文の紹介をしたりなどということはしていないのである。
(6)以上のように、被告は、全く事実に反することを、あたかも実際にあったことであるかのように書き立てているのである。
4 被告準備書面2、5項、6項について
(1)インターネットによる反論について
被告は、同準備書面5項(2)において、原告自身もインターネットにより被告に対する批判ないし反論を行っていると主張しているが、否認する。
原告は、訴訟の場で事実関係を明らかにすることを望み、また被告がホームページ上で訴訟係属後も次々に被告への誹謗を重ねていることにつきフェアなやり方ではないと考えている。そのため敢えて自ら本件に関してインターネットを用いて云々するのを避けているし、また知人らにそれを依頼するなどということも一切していない。
(2)被告の不法行為の悪質さ
ア.被告は、あたかも本件記事が他の学者の発表内容や方法論についての正当な批判であるかのように主張するのであるが、前述のとおり、建設的な批判は、まず相手の発表内容や用いた方法について、正しく把握し、それを正しく挙げたうえでおこなうべきものである。
イ.ところが、本件記事は、被告が、本セッションの座長という責任ある立場にあったにもかかわらず、原告の発言を十分に聞かず、理解することもできず、また「スライドに出た記事が、何新聞の記事かは分からなかったし、見出しも、よく分からなかった」(甲1、4枚目6行目〜)のは被告がそれを見なかったからにすぎないのに、それを棚に上げてあたかも原告が何新聞の記事なのか見出しもよく分からないような示し方をしたかのように記載したものである。
原告の発言がどのようなものだったのか確認することも、確認のうえで理解に努めることも、原告の示したスライド資料を確認することもせずに、いきなり被告ホームページ上に掲載したのである。
ウ.原告の発言を十分に聞くことは、被告が聞く気になれば容易なことであるし、座長としてセッションの進行を担うものとしては当然の責任である。仮に、開き逃したというのであれば、直接原告に確認すればよかったのである。
また、原告の発言を理解することも、東京大学環境安全研究センター教授、横浜国立大学大学院環境情報研究院教授を経て、現在は独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター所長を務め(乙1、p254奥付)、環境ホルモン問題についても多くの発言・執筆(例:乙1 p141〜)をしている高名な学者である被告にとっては、その気になれば容易なことであった。もし、その場で理解できなければ、まず本人ないしはその道 の専門家にどのような意味なのか尋ねてみることも被告にとっては容易なことであった。
さらに、本件記事を記載する前に、原告が用いたスライド資料を見て、何新聞の記事だったのか、どのような見出しの記事なのかを確認することはきわめて容易であった。なぜなら、環境省は本シンポジウムでパネリストが用いたプレゼンテーション資料をすべて環境省ホームページ上に公開していたからである(http://www.env.go.jp/chemi/end/2004/sympo7_mats.html)。
エ.被告が本件記事に原告の肩書きを誤って書いていることについて、被告は「この種の肩書きを正確に覚えるのが容易なことでないのは公知の事実と思うが、この程度の誤りから‥」と述べている(被告準備書面2、6項 p7)。原告は、原告の肩書きを正確に覚えろなどと主張しているのではない。
原告は、被告が常識的・基本的なマナーを守らず、きわめて容易にできる確認もしないで、研究者の肩書きを誤って書いて、それを顧みることなく「この程度の誤り」などと開き直るその態度を問題にしているのである。
研究者が、その立場(それが肩書きにあらわれる)を重視し、互いに尊重しあうのは常識的かつ基本的なマナーである。そして、被告にそのようなマナーに則って原告の肩書きを記そうという気持ちさえあれば、それを確認することはあまりにも容易にできることである。本シンポジウムのアブストラクトの講演者一覧にも記載されているし(乙4、p21)、本シンポジウムに先立ち、セッションの進行やアブストラクトの内容をめぐって原告と被告が電子メールのやりとりをした際に、原告は肩書きを付した署名をしてメールを送っていた(甲4ー3、2枚目下から4行目。甲4ー3は、原告が被告に送ったメールに対する被告からの返信である)。また、京都大学のホームページにアクセスしてもただちに確認できるのである。ましてや、被告は本シンポジウムのセッションの「座長」という役割を担っていたのである。パネリストを正式な肩書きで紹介することは、座長としての当然のマナーである。さらに、原告は、本シンポジウム開始前に、自らの肩書きについて、その名称の由来も含めて被告の目前で説明していたのであり、被告自身も、本件訴訟提起後においてなお、「この時の光景を鮮明に