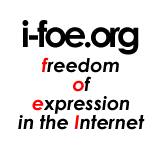本件訴訟に対する会としての見解
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
そもそも、裁判所で争う話ではない
訴訟のきっかけになったのは、原告の松井氏が行った国際シンポジウムでの発表に対し、座長の被告中西氏がウェブで発表内容をまとめて、批判するコメントを書いたことによる(ただし、以下が該当するだろう、というのは松井氏のメールから推定したものであって、裁判手続きの中では、口頭弁論2回目になっても、具体的にどの部分が名誉毀損なのかが特定されていない)。
パネリストの一人として参加していた、京都大学工学系研究科教授の松井三郎さんが、新聞記事のスライドを見せて、「つぎはナノです」と言ったのには驚いた。要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。
(中略)
学者が、他の人に伝える時、新聞の記事そのままではおかしい。新聞にこう書いてあ るが、自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべき ではないか。情報の第一報は大きな影響を与える、専門家や学者は、その際、新聞や TVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。でなければ、専門家でない。
松井氏の発表が実際にどのようなものであったのか、中西氏(に限らず一般の人)がこのように受け取るようなものであったのかどうかについては、これからの審理で明らかにされていくだろう。
しかし、どう考えても『「次はナノです」と言った』と書かれたことが、原告の社会的名誉を低下させるとは思えない。どんな口頭発表であっても、資料の提示の仕方や話の持って行き方や発表者の口調などが原因で、発表者の意図とは異なった印象を与えたり、聴衆が誤解したりすることは普通にあり得る。こんな発表がありました、ということがウェブに掲載されて、内容が発表者の意図や言ったはずのことと違っていたとしても、名誉毀損の訴訟の原因になるというのはおかしい。意図が伝わらなかった原因は、発表者にだってあるはずである。自分の発表の下手さ加減を棚に上げて相手を訴えたところで、一体何が得られるのだろうか?訴状を書くよりも「発表の意図と内容はこうでした」と、もう一度説明して理解を求める方が先だし、建設的ではないだろうか。
国際会議でどんなことが話し合われたかとか、発表を聞いてこう思った・こう考える、といった内容が、プロの研究者から出てくることは、その分野を専門としない人にとっても望ましいことである。今、専門家の間で何がどのように話し合われているか、知る手がかりになる。また、一口に専門家といっても、企業や特定団体のご用聞き学者から、公正中立を貫く人まで、立場も利害関係もさまざまである。専門家同士の批判はどんどんやって内容を公表してもらった方が、結局は精度の高い情報を得ることができる。議論の途中で何らかの行き違いが生じたとしても、議論の内容がその専門分野に関するものである限り、専門家たるもの議論で解決すべきであって、裁判所に持ち込むものではない。専門の内容の議論が行き違ったからといって安易な提訴を許す社会になってしまっては、専門家を必要以上に萎縮させ、その結果専門家から発信される情報も減ってしまい、結局は社会全体の損失になる。
原告の松井氏は京都大学教授である。大学で学生相手に講義しても、狙ったことがその通り全員に伝わるとは限らない。松井教授は、学生が「松井教授の講義はこんなだった」とウェブに書いて、それが講義の意図やしゃべった内容と違っていたら、名誉毀損で学生を訴えたりするのだろうか。今回の提訴は、この状況で学生を訴えるというのと同程度にナンセンスなものではないだろうか。
まず当事者がきちんと交渉すべきだ
本件訴訟の経緯を見ればわかるように、提訴に至るまでの間、当事者の間ではまともな交渉が行われていない。
松井氏は中西氏へ抗議のメールを送ったが、同時に多数の友人にCc:している。話を広めようとする意図は感じられても、当事者同士で解決に向けて話し合おうという姿勢がみられない。
松井氏が提訴の準備をしていることをメールで中西氏に告げたのは、訴状提出の前日である。それまで、「訴えるぞ」とも「名誉回復に協力せよ」とも、何も主張していない。一方、プレス向けの準備は前から進めていたようで、提訴したその日のうちに、ウェブ版ではあったが新聞で報道が行われ、翌日紙メディアの方にも出た。あまりにも手際が良すぎる。これでは、最初から訴えることだけを目的にしていたとしか思えない。
民事訴訟は、紛争に法律を適用して解決するための手続きであが、交渉の手段の一つでもある。訴訟の前に当事者の交渉があるのが普通で、訴訟が始まってからでも、裁判所の外で当事者は自由に交渉してもよく、合意すれば訴訟をやめてもかまわない。
一般に、不法行為を原因とする損害賠償請求事件の場合は、原告が、不法行為があったことと、賠償すべき損害が存在することを、裁判官の前で立証することになる。しかし、名誉毀損の場合は、ある内容の文書を公開されたという「名誉を毀損した事実」そのものについては明確であり、通常、争いが生じることはない。裁判では、被告が「その表現は名誉毀損にあたらない」「公益目的で摘示した事実だから責任を負う必要はない」といったことを立証していくことになる。
ところが、本件訴訟の場合は、口頭弁論を2回やっても、中西氏の書いた文章のどの部分が名誉毀損にあたるのかという特定がなされないままである。これは、名誉毀損の訴訟としてはきわめて異常なことである。原告は「全体として名誉毀損になっている」と曖昧な表現を繰り返すばかりである。
謝罪文を公表して賠償金を払えという要求だけは、訴状でやっと明らかになったが(まあ、これがないと訴状が書けないのだけれど)、「何が問題だったのか」については棚上げされたままで、裁判がさっぱり進まない。そもそも、元の表現が名誉毀損に該当するのかどうかさえ怪しくなってくる。
松井氏は、「中西氏がシンポジウムの会場で何も言わずに批判をホームページに書いた」と言って、中西氏を非難している。この非難は全くの的外れである。研究者が国際シンポジウムで発表するということは、自身の見解について広く世に問うということである。その結果、ウェブに限らず後からどんなメディアで批判や議論がなされたとしても、それは仕方のないことである。もし、間違った批判や議論がなされた場合には、今なら簡単にウェブで広く情報発信できるのだから、自らの発表内容を補足する情報を出して、再び世に問えばよいだけである。批判も議論もされたくないというのなら、最初から発表なんかしなければいい。
さらに、ネット上の表現の場合は、従来のメディアと異なり、基本的に双方向である。ウェブサイトで行うという一見一方通行に見えるものであっても、いつでも内容を訂正できるし、抗議する側も自身のウェブサイトで意見表明して対抗できる。このことをよく理解した上で、直接関係のない他人にメールをばらまいたり、提訴することを前日まで黙っていたりしないで、まずは当事者同士で、何が問題でどうしてほしいのか、きちんと話し合うべきではなかったか。
なお、今までの多くのインターネット上の記事をめぐる名誉毀損裁判では、かなりのやり取りがあったり、長期間に渡って記事が掲載された、という事例がほとんどである。しかし、今回は、一つの記事だけで、被告がじっくり考えて結論を出しますと言っている間に提訴されている。確かに法的には一回でも千回でも同じではあるが、社会常識からは、こんなことをしていいのか、大いに疑問である。
ネットもネット以外も同じ扱いが望ましい
実はこれが、この訴訟の背後にある一般的な問題だと考えている。
ネットというのがメディアであることは疑いがないが、いわゆるマスコミに比べると、急に出てきた新参者であり、その評価はまだ固まっていない。このため、しばしば、「マスコミは信用できるが、ネットワーク情報は信用が無いのだから……」といった話が出てくる。
どうも、松井氏は、国際会議で発表した内容について、ネット上であれこれ批判やコメントをすること自体を好ましく思っていない節がある。
さらに、原告代理人の中下弁護士は、 「特に解説を加えずに新聞記事を紹介した」といった批判が名誉毀損を構成するのかどうかを議論するときに、「 新聞記事は多くの人手によって作られるのだから、客観的事実である」と考えているようである。準備書面では、
「新聞は、往々にして、ニュース性のあるものを優先して、しかも刺激的な見出しを付けて掲載するのであるから、センセーショナルな見出しのついた記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどということは、参加者に誤った印象を植え付ける危険性が高く、専門家としてのプレゼンテーションとしては適切でない」との被告の見方自体も、極めて一面的なものと言わざるを得ない。
新聞報道においては、記者はもちろん客観的な事実に基づくものかどうかの観点から二重三重のチェックが行われている。その上で、さらに意見が対立しているような場合には、偏った報道を回避するために、異なる立場からのコメントを掲載するなどして公平性に配慮されているのである。
と述べている。実は、これは大きな間違いなのだ。科学技術関係で間違った報道がなされることはしばしばあるし、事件の取り上げ方が新聞によって異なるとか、新聞にとって都合の悪いことはそもそも滅多にとりあげられないということは、既にいろんな場所で指摘されている。
インターネット経由で発信される情報について、現役の朝日新聞の記者である団藤氏は、「インターネットで読み解くNo.25 インターネット検索とこのコラム」で次のように述べている(これは、1990年前後の状況を説明したものである)。
新聞メディアと読者の現状を、当時の私はこんなふうに整理した。高度成長期に入るまでは、新聞がカバーしていた知のレベルは社会全体をほぼ覆っていた。技術革新の進展と裏腹の矛盾、歪みの集積は社会のあちこちに先鋭な問題意識を植え付け、新聞がふんわりと覆っていた知の膜を随所で突き破ってピークが林立するようになった。特定のことについて非常に詳しい読者が多数現れ、新聞報道は物足りない、間違っているとの批判がされている。新聞の側はそれに対して真正面から応えるよりも、防御することに熱心になった。読者とのギャップはますます広がっている。なぜなら、知のピークはどんどん高くなり、ピークの数も増すばかりだから。
さらに、同じシリーズのコラム「時評「この国のメディアが持つ構造死角」」においても「全体としての知の水準が新聞を超えているのではないが、個々人が関心を持つ特定の問題意識では、本当にあちこちで凌駕されている。」との記述がある。これが、新聞報道を行う側の実感の1つなのだ。
ある分野の専門家(必ずしもプロの学者を意味しない)が、ネット上で情報発信するのであれば、容易に、新聞報道を超える内容を発信することができるはずである。また、それが可能であるところに、ネットの利点と魅力がある。ネットだから信用できないとか、新聞や書籍だから信用できるという区分けは無意味で、内容によって判断するべきである。
学会はそもそも関係ないはず
本件訴訟で原告が提出した上申書には、
日本内分泌撹乱化学物質学会事務局に対し、訴状別紙(1)記載の謝罪広告を同学会が発行するニュースレター「Endocrine Disrupter NEWS LETTER」に掲載する件につき確認しました。その結果、当事者からの依頼または裁判所の判決があれば同謝罪広告を同ニュースレターに掲載する、その場合の掲載料は無料である、との回答をいただいております。
とある。学会のニュースレターであれば、裁判所の判決があれば「何でも掲載する」はあり得ないだろう。ということは「この裁判について、被告の謝罪文に限って」と解釈できるわけで、記事掲載の一般ルールでは無いと思われる。要するに「日本内分泌撹乱化学物質学会(通称環境ホルモン学会)は、訴状もまだ被告に届いていないような事件について、原告側の立場を支持している」と受け取ることができる。しかし、中西氏は松井氏個人の発表については批判したけれども、環境ホルモン学会については何も書いていない。議論にも訴訟にも無関係な学術団体が出てくるのはおかしいし、松井氏が学会まで巻き込もうとしているのであれば、それは松井氏の大きな間違いというものだろう。